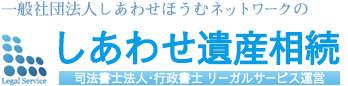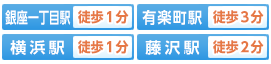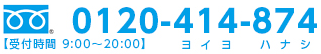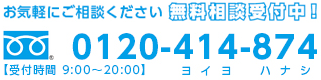「負動産(ふどうさん)」とは、売却が難しい、あるいは維持管理にコストばかりかかるなど、持っていることが“負担”にしかなっていない不動産のことです。
地方の空き家や山林、田畑などが該当することが多いです。
そのような負動産を処分や維持管理をするにはどのようにすればよいでしょうか?
<負動産の処分・維持管理>
負動産は以下の方法で処分や維持管理を検討しましょう。
1.売却(できる場合は最優先)
不動産会社に依頼して購入者を探します。
まずは不動産会社に相談し査定を依頼しましょう。
ただし、市場価値がない場合、売却価格「1円」や売主が一部の将来経費を負担して買主に先渡しするなど実質マイナス価格で売る事例も考えられます。
また、『0円不動産専門サイト』や『空き家バンク』などを活用することも考えられます。
不動産会社に依頼しない場合、隣地所有者に売却を打診してみるのも良いでしょう。昔から「隣の土地は借金してでも買え」という格言があり、隣人にとっては利用価値が増えることも多いので、売却が成立することも少なくありません。
2.寄付・贈与
自治体・NPO・個人へ寄付することも考えられます。ただし、自治体は基本的に受け取りに消極的なことが多いものです(維持費がかかるため)。
また、親族への無償譲渡(贈与)なども考えられます。ただし、受領する親族に贈与税がかかる可能性もあり、税理士に相談するなど注意をしましょう。
3.解体して更地にする
遠方で管理ができない場合、古屋を解体して更地にすることも検討しましょう。
ただし、メリット・デメリットがあるため、慎重に検討が必要です。
<更地にするメリット>
・建物の管理が不要になり、老朽家屋の倒壊や火災のリスクが減る
・更地なので老朽家屋がある場合に比べて管理がしやすい
・更地の方が利用しやすいため、すぐに売れることもある
<更地にするデメリット>
・解体費用がかかる(木造30坪で100〜150万円程度が一般的)
・固定資産税が上がる(固定資産税は3倍になる可能性)
・程度の良い建物があった場合、更地にしたことで売れなくなることもある
・売却時の譲渡税が増えることもある(3000万控除の適用など)
・草刈りなどの維持管理は必須
4.管理委託
建物を取り壊さない場合、管理もせずに放置はNGです。倒壊や火災のリスクがあり、老朽化が著しい場合は特定空き家の認定などにより、行政代執行の発動や固定資産税の増額のリスクもあります。
どうしても自身で管理できない場合、地元の不動産管理会社などに管理を委託し、処分のタイミングを待つことも必要になります。
5.相続放棄
もし負動産が相続財産の場合、または将来的に負動産を相続することが見込まれる場合、相続放棄を検討しましょう。
相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述し、相続人の地位を外れることで、負動産に関しての権利義務がなくなるため、維持管理を行う必要がなくなります。
ただし、他の有用な資産も相続財産の場合、その有用な資産も放棄されるため慎重に判断する必要があります。
また、負動産を既に占有し維持管理をしていた場合、相続放棄後も新たな相続人や財産管理人などに引き渡すまでは管理をする義務がありますので注意しましょう。
6.国庫に帰属させる
2023年より「相続土地国庫帰属制度」により、不要な土地を国に引き取ってもらう制度が開始されました。
諸条件はなかなか厳格(基本的に平坦な更地しか受け付けない・数十万の費用がかかる)ですが、負動産の管轄地の法務局に相談をすることも検討しましょう。
☆相続土地国庫帰属制度 法務省:相続土地国庫帰属制度について
しあわせほうむでは、相続相談・生前整理などのご相談で、不動産処分についても多くご相談を受けております。お気軽にしあわせほうむ司法書士、行政書士にご相談ください。