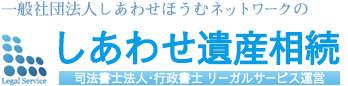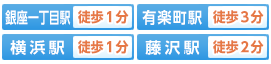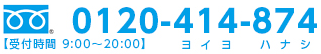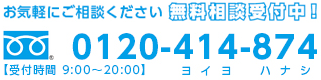相続手続きにあたり、まず最初は戸籍収集から開始となります。
お亡くなりになられた方の相続関係を証明するため、出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得する必要があります。
取得した戸籍類は、相続登記・預金解約を始め、ほとんど全ての相続手続きに使用できますので、取得の進め方について解説します。
1.お亡くなりになられた際の戸籍謄本を取得
お亡くなりになられた際、本籍地に市区町村役場に死亡届を提出し、しばらく後に死亡の記載がなされた戸籍謄本(除籍謄本)が発行されますので、こちらを取得しましょう。
2.改製原戸籍など古い戸籍謄本へとさかのぼって取得
現在戸籍の記載に、「直前の戸籍謄本の記載」があるので、市区町村役場の戸籍課の方と相談しながら、「前の戸籍」「その前の戸籍」と取得を進めましょう。
「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」などさまざまな種類の戸籍謄本がございます。
『出生時の戸籍謄本』まで遡るようにしましょう。
3.配偶者・子や(場合により)兄弟姉妹など他の法定相続人の戸籍謄本を取得
お亡くなりになった方に配偶者がいる場合、子がいる場合は、配偶者や子の戸籍謄本、配偶者や子がいない場合、兄弟姉妹・甥姪などが相続人になるので、それらの方々の戸籍謄本を取得しましょう。
この場合、親や祖父母の戸籍も必要になることがあります。
4.市区町村役場の発行窓口で必要なもの
発行にあたり、請求者の本人確認書類(運転免許証など)・請求理由の明記(例:相続手続きのため)・委任状(他人が代理で請求する場合)・つながりのわかる戸籍謄本や住民票などが必要となる場合があります。あらかじめ戸籍課に確認しましょう。
相続戸籍の収集は、明治時代の手書きの戸籍謄本まで遡る、さまざまな親族の戸籍を取得する必要があるなど、難解なものが少なくありません。
司法書士・行政書士は相続手続きの専門家。お気軽にお問い合わせください。