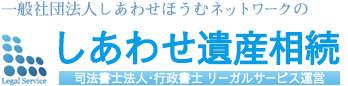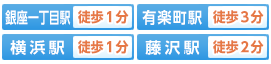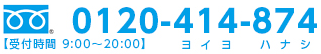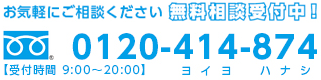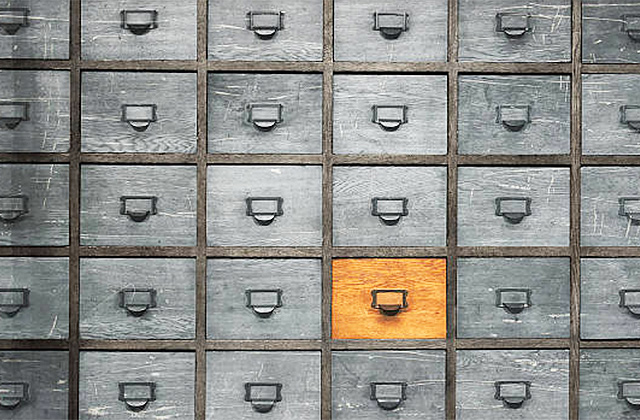
2024年3月より、相続手続きの戸籍収集は、相続人に対する広域交付制度が開始され、相続人は日本全国の戸籍を取得できるようになりました。
格段に利便性が向上しましたが、取得すべき戸籍謄本については今も昔も変わりません。
相続手続きに必要とされる「出生から死亡までの戸籍謄本」について、何種類もございますので、どのような種類の戸籍謄本があるか、戸籍制度を確認してみましょう。
1.明治時代の戸籍制度(1872年:明治5年)
1872年、日本で初めて全国統一の戸籍が編成された戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)と言います。
氏・名・性別・年齢・続柄・出身地・戸主などが記載されております。
2.戸主制度の戸籍(1898年:明治31年)
1898年、明治民法の家制度・戸主制度を戸籍に制定した戸籍謄本です。
氏・名・性別・年齢・続柄・出身地・戸主などが記載されております。
家督相続(戸主の地位と家財の継承)により、相続は、主に長男などが家督を継ぐ形で戸籍謄本に記載されております。
3.戦後の戸籍(1947年:昭和22年)
終戦後の1947年、日本国憲法施行とともに民法が改正され、家制度・戸主制度の廃止を反映した戸籍が制定されました。
相続は個人単位の相続に変更され、戸主制度の廃止により配偶者や子どもなど法定相続人が相続権を有することが原則となりました。
4.現行制度(平成・令和)
1994年(平成6年)以降、戸籍のコンピューター化が始まり、徐々に市区町村役場の戸籍謄本が「横書き」の印字に移行されるようになりました。
2024年(令和6年)、相続人に対する広域交付制度が開始され、相続人は日本全国の戸籍を取得できるようになりました。
相続手続きには、「出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本などの呼称もあります)」が必要とされ、戸主制度の戸籍謄本から現在に至るまでの戸籍謄本が必要となるケースが多数です。
相続戸籍収集の際には、これらの戸籍謄本の種類を念頭に置いて収集されることがおすすめです。
司法書士・行政書士は、相続手続きの専門家。お気軽にお問い合わせください。