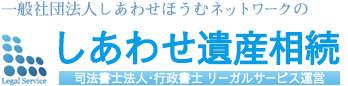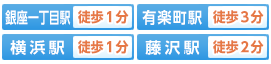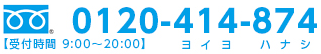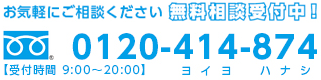故人所有のマンションを相続した際、さまざま手続きが必要となります。
以下主な手続きの流れを説明します。
1.相続人の確定(戸籍類の収集)
相続人を証明するため、市区町村役場で以下の戸籍類を収集しましょう。
2024年より、相続人の広域交付制度が開始され、相続人であれば最寄りの役場で故人の戸籍謄本が取得できます。
<遺産分割協議を行う場合の収集書類>
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・名義取得者(相続人)の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産税評価証明書
2.遺言書や遺産分割協議書を用意
遺言がある場合は遺言書を、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合い、取得者を決定する場合は遺産分割協議書を用意しましょう。
自筆の遺言書(自筆証書遺言書)の場合は、原則として家庭裁判所の検認手続きを行う必要があります。ただし、法務局保管制度を利用した遺言書の場合は法務局にて遺言書情報証明書を取得し、こちらを遺言書として用意しましょう。
公正証書遺言書の場合は、遺言書の正本または謄本を用意しましょう。手元にない場合は公証役場で発行が可能です。
遺産分割協議書を作成する場合、故人の特定事項(氏名・生年月日・死亡日・本籍や住所など)、マンションを登記簿通りに記載し、取得者の氏名や取得割合を明記の上、相続人全員が署名・押印(実印)をしましょう。数ページにわたる遺産分割協議書には各ページ間に割印をしましょう。
3.法務局の相続登記
上記の書類を法務局に提出し、相続登記を行いましょう。2024年より相続登記が義務化となっております。3年以内に相続登記を行いましょう。
申請先:マンションの住所地を管轄する法務局
4.管理組合への連絡(マンション特有)
マンションの管理組合に相続した旨を連絡し、所有者名簿の変更をしましょう。
同時に管理費・修繕積立金の支払者の変更手続きも行いましょう。
(手続きは管理組合や管理会社毎に異なるのでお早めに取り合わせをしましょう)
5.相続税の申告・納付(必要な場合)
故人の総資産が、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税申告や場合により相続税の納付が必要となります。10か月が申告期限のため、早めに基礎控除額を超えているか確認をしましょう。
※相続登記の登録免許税計算は「固定資産税評価額」、相続税の評価額は、敷地部分は「路線価」、建物部分は「固定資産税評価額」で計算されるため、算定が難しいマンションもあります。早めに相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に相談しましょう。
しあわせほうむの相続専門家は司法書士(相続登記)、税理士(相続税)がノウハウ豊富にマンション相続の手続きを行っております。
お気軽に、司法書士・税理士にご相談ください。