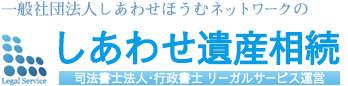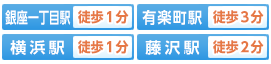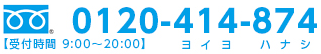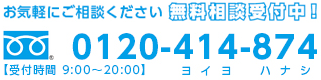ずいぶん昔、遠くへと離れ、かなりの年月を経た田舎の土地。そのような土地でも2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしており、相続を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
今回はそのような土地を相続した際の相続登記についてご説明します。
1.相続関係を確定
まず、誰が相続人かを確定するため、下記の戸籍謄本類を取得しましょう。
・被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合)
・相続不動産の固定資産税評価証明書
※故人の戸籍謄本は、相続人が取得する場合、広域交付制度により最寄りの市区町村役場の戸籍課などで取得可能です。
2.遺産分割協議
相続人が複数おり、誰が特定の方が取得をする場合など法定相続割合以外の取得割合となる場合、その土地を誰がどのように相続するかを相続人全員で話し合って決定し、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名のうえ実印を押印します。
その際、相続人全員の印鑑登録証明書も必要となります。
(遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要です。)
3.相続登記の申請
土地のある地域を管轄する法務局に、①②の書類と共に相続登記の登記申請書を提出し、相続登記を申請しましょう。
※登録免許税は、原則として固定資産税評価証明書記載の評価額の0.4%ですが、評価額が100万以下の土地の場合、免税措置が適用され、登録免許税は「0円」となります。(租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税)
なお、1筆あたりの土地評価額が100万を超過したり、100万以下の評価額でも不動産が建物の場合は原則通り0.4%の登録免許税となるので注意しましょう。
2024年より相続登記が義務化され、田舎の土地でも相続登記を行う必要がございます。しあわせほうむの司法書士は全国の相続登記を手掛けており豊富な経験がございます。
お気軽に当ホームページから司法書士までご相談ください。